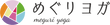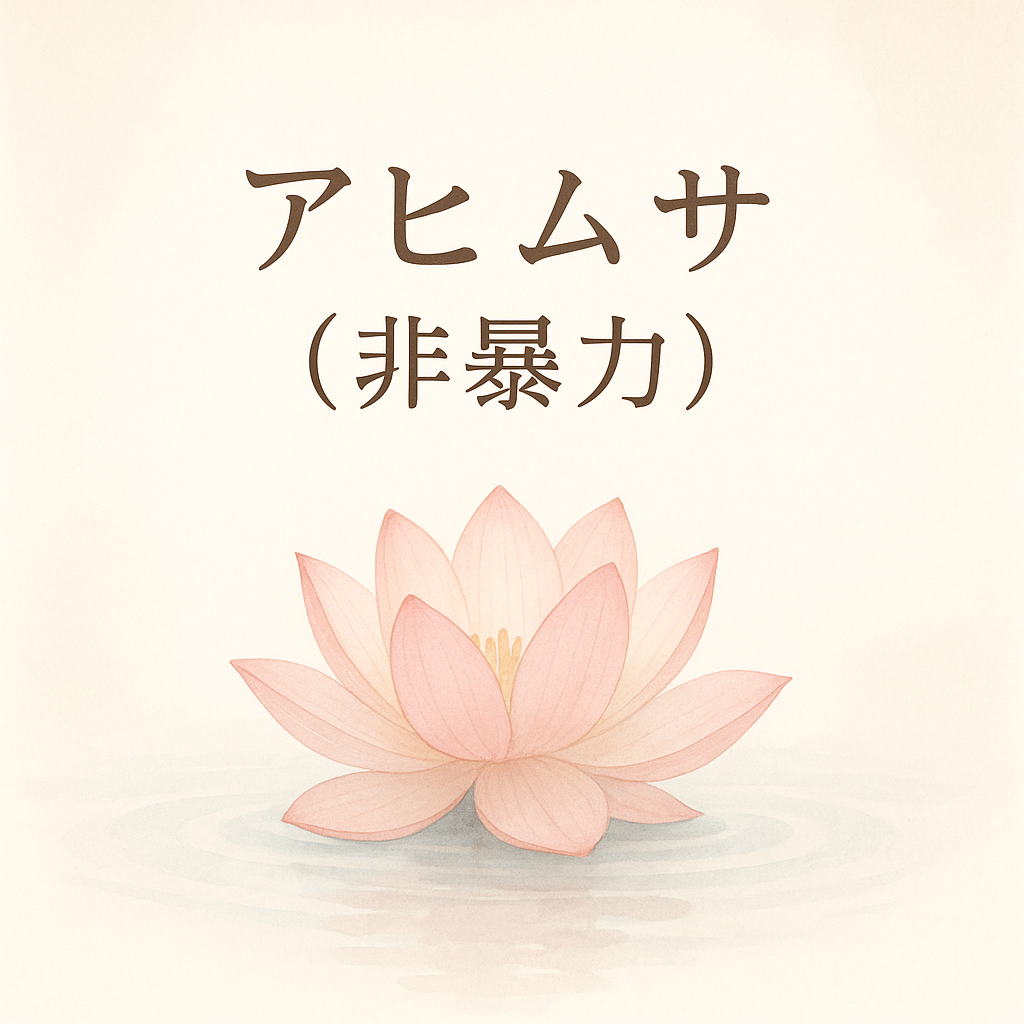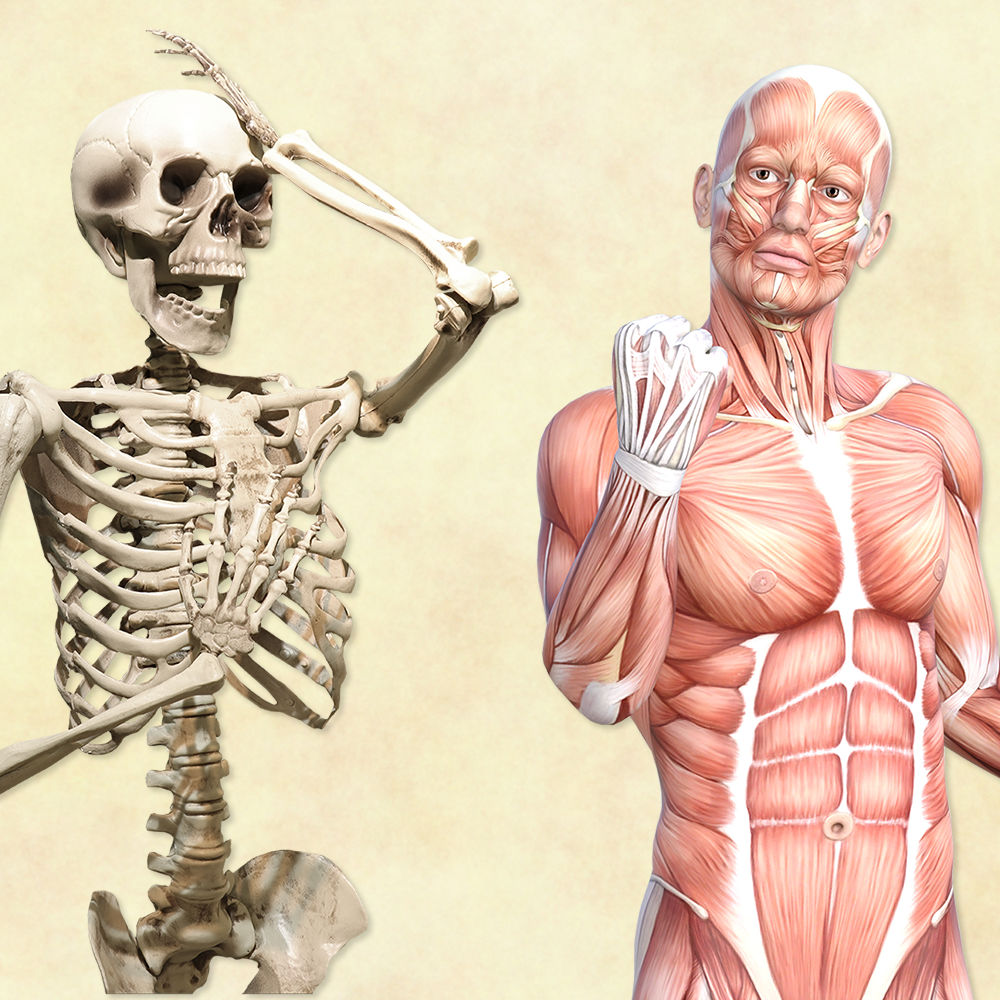ヨガを学んでいると必ず出会う言葉の一つに 「アヒムサ(Ahimsa)」 があります。
サンスクリット語で「非暴力」を意味するこの概念は、単に「人を傷つけない」という道徳的な戒めにとどまらず、自己との向き合い方、人間関係、さらには社会や地球との調和までを含んでいます。
アヒムサの意味と背景
「アヒムサ」とは、サンスクリット語の「ヒムサ(暴力・害を与える)」に否定を表す接頭辞「ア」がついた言葉です。つまり「害を与えない」「傷つけない」という意味になります。
アヒムサの思想はインドの精神文化全般に広がっており、仏教やジャイナ教にも深く影響を与えました。
特にジャイナ教では「アヒムサ」は徹底した戒律として実践され、後にガンディーによる非暴力抵抗運動の哲学的基盤にもなりました。
暴力とは何か?
「非暴力」と聞くと、殴る・蹴るといった身体的な暴力を連想しやすいですが、ヨガ哲学におけるアヒムサはもっと広い意味を持っています。
-
言葉の暴力
批判的な言葉や皮肉、無神経な発言も他者を傷つけます。直接的でなくても、心に深い傷を残すことがあります。 -
思考の暴力
嫉妬や怒り、憎しみといった感情を抱き続けることも、目に見えない暴力です。思考のエネルギーは言葉や態度に現れ、周囲に影響を及ぼします。 -
自分への暴力
自分を過度に責める、休まない、身体を酷使するなどもまた「暴力」の一形態です。アヒムサは他者に対してだけでなく、自分自身に対しても適用される考え方です。
アヒムサの実践方法
1. 言葉を選ぶ
日常で最も簡単にできる実践は「言葉の使い方」を意識することです。相手を否定せず、優しさや理解を込めて言葉を選ぶことは、アヒムサの第一歩です。
会話の中で「ありがとう」「大丈夫だよ」といった言葉を増やすだけでも、空気は穏やかに変化します。
2. 思考を観察する
怒りや不満が湧いたとき、それを抑え込むのではなく「いま自分の心にこんな感情がある」と認識することが大切です。
瞑想や呼吸法を通じて心の波を観察すると、感情に飲み込まれずに距離を取ることができます。
3. 自分を労わる
夜更かしや暴飲暴食、過剰なストレスは自分への暴力です。
十分な休養、バランスの取れた食事、ヨガや運動で身体を整えることは「自己への非暴力」となります。
4. 他者との関わりでアヒムサを意識する
競争や比較から生まれる攻撃性を手放し、相手の立場や感情を尊重すること。
ヨガのクラスでも「ポーズを無理にやらない」「できる人と比べない」という態度がアヒムサの実践です。
アヒムサがもたらす効果
心の安定
攻撃的な感情を手放すことで、心は静まり、ストレスや不安が減っていきます。内面的な平和はそのまま瞑想やヨガの深まりに直結します。
人間関係の調和
相手を尊重し、否定せずに接することで信頼関係が築かれます。小さな言葉の積み重ねが、家庭や職場の雰囲気を変えていきます。
社会全体への広がり
個人がアヒムサを実践すれば、その優しいエネルギーは家族、地域、社会へと広がっていきます。非暴力は決して消極的な態度ではなく、愛と理解をもって能動的に行動する姿勢です。
アヒムサ(非暴力)メンタルヘルス実践講座のご紹介
めぐりヨガではアヒムサ(非暴力)メンタルヘルス実践講座を開催しています。
日時:9/11(木)
9:30〜15:00(お昼休憩あり)
1日完結する集中講座となります。
この講座を受講することで、自分や他者に優しくなれます。
この講座の詳細はこちらをご覧ください。