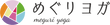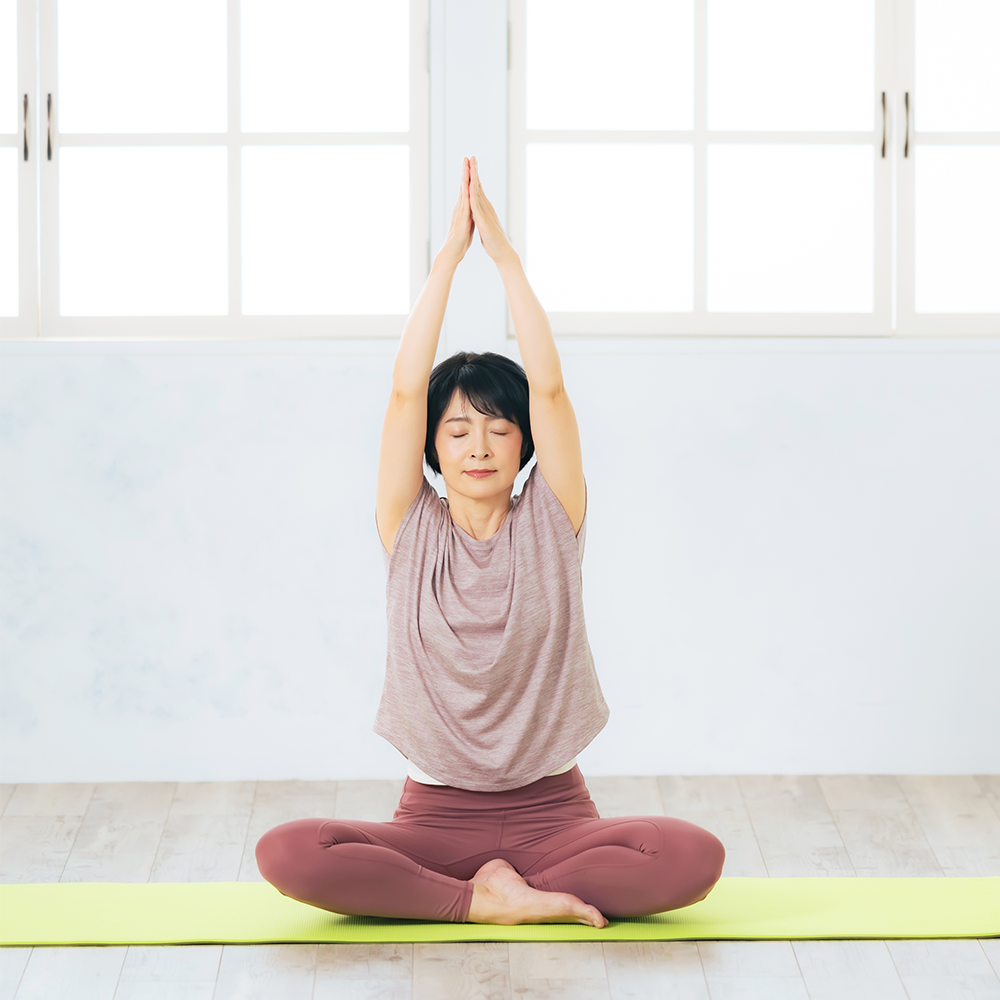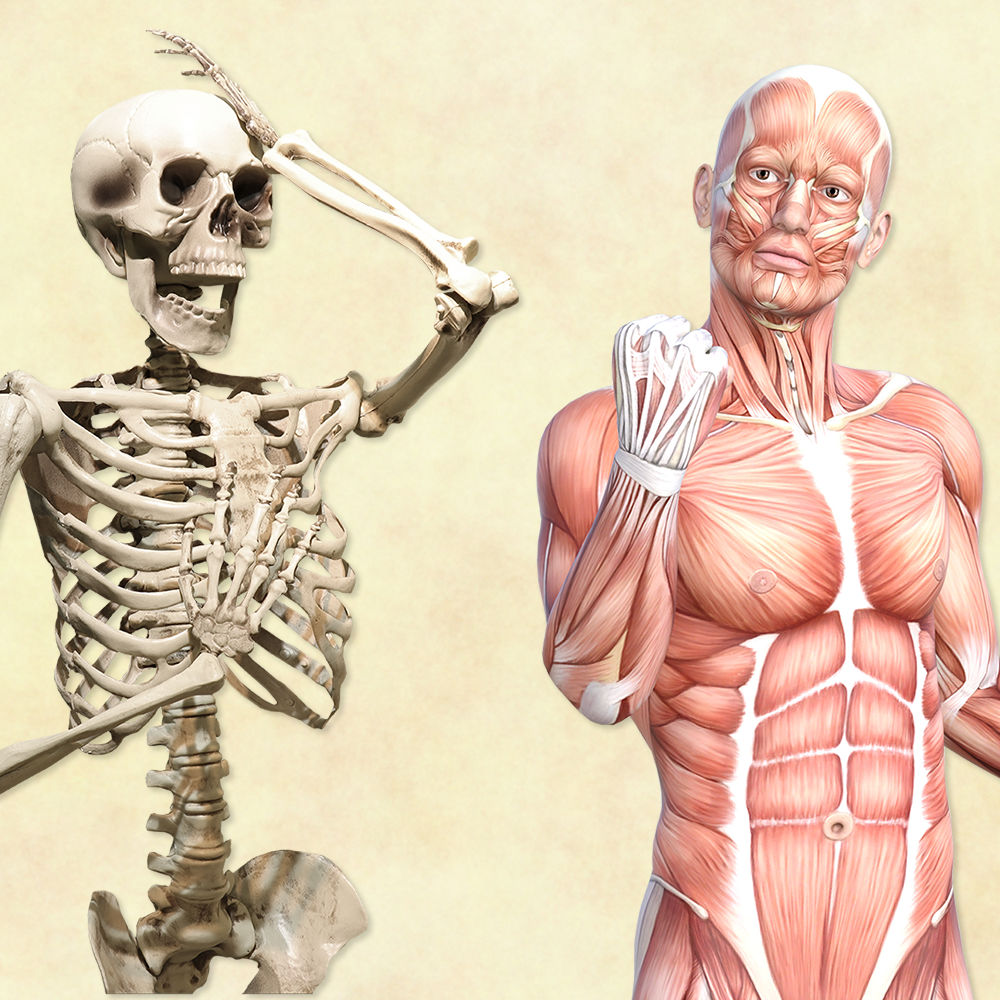夏の盛り、8月中旬。この時期、日本では「お盆(盆)」という大切な行事が営まれます。
お盆は、亡くなったご先祖様の霊が一年に一度家族のもとに帰ってくるとされ、その霊を迎え、もてなし、また送り出すまでの一連の風習です。
古くから受け継がれてきたこの行事には、私たちの命のつながりや、感謝の心、家族の絆といった大切な価値観が込められています。
お盆の起源と意味
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」。
その由来は、仏教の教えの中にある『仏説盂蘭盆経(ぶっせつうらぼんきょう)』という経典に遡ります。祖先供養の行事の根拠となっている短い経典です。
この経典では、釈迦の弟子が、亡き母が餓鬼道(※)に落ちて苦しんでいるのを救いたいと願い、お釈迦様に助けを求めたという話が語られています。
※餓鬼道:強い欲や執着の報いで、飢えと渇きに苦しむ世界
そこで釈迦は僧侶たちを招いて供養をするよう教え、弟子の母は成仏できたとされます。これが盂蘭盆会の始まりです。
「盂蘭盆(うらぼん)」という言葉はサンスクリット語の「ウランバナ(逆さ吊りの苦しみ)」に由来すると言われており、苦しんでいる霊を供養するという意味が込められています。
やがてこの仏教行事は日本古来の先祖信仰と結びつき、現在の「お盆」として発展してきました。仏教的な供養の意味合いと、祖先の霊を敬い迎える日本独自の風習が融合したものです。
お盆の時期と地域差
多くの地域では、お盆は「8月13日から16日」に行われます。一部の地域では旧暦に基づいて「7月13日から16日」に行う「新盆(しんぼん・にいぼん)」もあります。
この時期になると、会社や学校はお盆休みとなり、都会に住む人々がふるさとに帰省して、家族とともに過ごす風景が広がります。
お盆の風習と行事
お盆には様々な風習がありますが、以下のような流れが一般的です。
1. 精霊を迎える「迎え火」
8月13日の夕方、ご先祖様の霊を自宅に迎えるために「迎え火」を焚きます。昔は家の門口で小さな火を焚き、霊が迷わず戻ってこられるように目印としました。現代では省略されることもありますが、迎え火には「家族の元へ戻ってきてください」という思いが込められています。最近ではローソクや提灯を使う家庭もあります。
また、キュウリとナスに割り箸を刺して、馬と牛を模した「精霊馬(しょうりょううま)」を供える風習もあります。キュウリは早く帰ってこられる馬、ナスはゆっくりと戻る牛とされ、ご先祖様の旅路を助ける役目を担っています。
2. 仏壇やお墓の掃除・お供え
お盆の前には仏壇を清掃し、花や果物、お菓子などをお供えします。特に初めて迎える「新盆」では、白提灯(しろちょうちん)を飾り、僧侶を招いて法要を営むこともあります。
また、お墓参りも重要な行事です。家族そろって墓地を訪れ、墓石を掃除し、線香や花を供えます。静かに手を合わせる時間は、亡き人を偲び、自分自身を見つめ直す機会にもなります。
3. 精霊送り・送り火
8月16日ごろ、ご先祖様をあの世へ送り返す「送り火」が焚かれます。
京都の「五山の送り火」は全国的に有名で、大文字の火が山肌に浮かび上がる壮麗な光景は、幻想的でどこか神聖な空気をまとっています。
地方によっては、灯篭流しや踊りとともに精霊を送る地域もあり、その土地ならではの風習が色濃く残っています。
お盆に込められた心
お盆は単なる「夏のイベント」ではなく、いのちの根源に向き合い、過去と未来をつなぐ大切な時間です。
亡き人への感謝、生きていることへの感謝、自分という存在が多くの命のつながりの中にあるという実感が湧いてきます。
また、「供養」だけでなく「共に過ごす時間」でもあります。
精霊が戻ってきて家族と食卓を囲み、団欒のひとときを楽しんでいると信じられています。故人の好きだった食べ物を供えたり、思い出話に花を咲かせたりすることも、大切な供養の一つです。
お盆は、亡き人を偲び、命の循環に思いを馳せる、深い祈りの時間です。
命を想い、今を大切に生きるためにもご先祖様へ合掌しましょう。